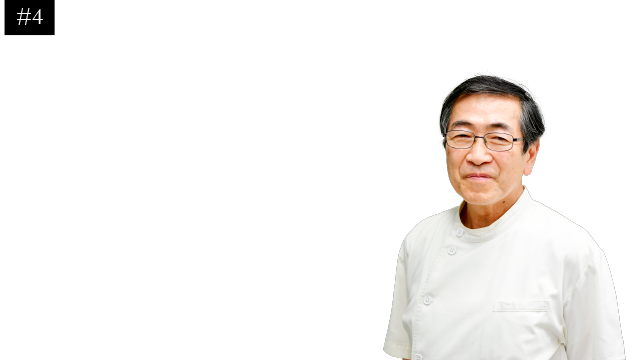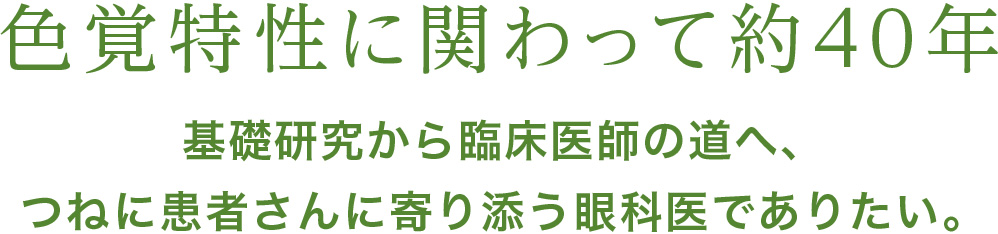尊敬する教授との出会いによって、色覚の道へ
名古屋大学で学んでいた時、医療人としても一番尊敬していた方が、市川宏教授です。本当に優しくすばらしい先生でした。難しい患者さんが次々と送り込まれるのですが、いつも、その患者さんに最適な対応をしておられ、皆さん満足して帰っていかれました。市川教授の専門は色覚の臨床研究で、市川教授が名古屋大学眼科に赴任された直後に私が眼科に入局したという経緯もあり、私も色覚を専門とするようになりました。
以前は、日本中の学校で毎年の定期健康診断時に色覚検査が行われていました。全児童生徒が対象であった時期もありましたが、対象学年が徐々に減り、1995年には対象は小学校4年生だけになってきました。色覚による社会差別の問題も表面化し、2002年には学校保健法施行規則が変更され、学校での健康診断の必須項目から色覚検査が削除され、それ以降、色覚検査はほとんど行われなくなりました。大学などへの入学制限も徐々に解除され、現在ではほぼ撤廃されています。
実は、学校での色覚検査を最初に中止したのが名古屋市です。名古屋市の学校医眼科会が名古屋市の教育委員会を巻き込んで、「色覚検査は差別を助長するからやめよう」となり、その動きが全国に波及していきました。市川教授の指示もあり、私も名古屋市の色覚検査をずっと手伝っていましたので、色覚検査が中止されることになった片棒を担いだ形になりました。余談ですが、市川教授が色覚を専門にされたのは、鉄道病院におられたことが大いに関係しています。鉄道の運転士は遠くにある信号の色の判断をしなければならなかったため、市川教授は運転士たちの色覚を検査するためのランタンテストや、色覚の検査表を作っておられます。
名古屋市では2002年度から、全国的には2003年度から、学校で一斉に行う色覚検査は中止になりましたが、これによって色覚についての認知度が下がり、自分の色覚特性を知らない若い人が増えてきました。それに伴い、色覚異常が原因のトラブルが問題になってきました。例えば、美容師として就職したにもかかわらずヘアカラーの色の見分けがつかない新人、あるいは色覚異常だとわかり自衛隊志望を断念した学生など、多数あります。いずれも、自分の色覚特性を知っていたら避けられたトラブルです。
このため、最近では色覚検査が見直され、適正な色覚検査への模索が続いています。2014年に学校保健安全法施行規則が改正され、色覚検査の必要性を児童生徒やその保護者に学校現場で周知し、広く色覚検査の希望者を募るようにとの指示が出され、2年の猶予をもって2016年から実施されました。私自身も折にふれ色覚検査の啓発活動に参加していますが、色覚の問題について適切な対応をするには、社会の誰もが色覚や色覚異常について正しく知ることがまず大切だと思います。
ところで「色覚異常」という言葉について、日本遺伝学会は「色覚多様性」という表現を提案しています。「色覚特性」という言葉も一部で推奨されていますが、名称が変更された訳ではありません。「色覚多様性」や「色覚特性」という言葉は正常色覚の人も含んだ総括的な表現ですので、適切ではありません。何かもっと良い名称が望まれるところです。

医師国家試験前の打合せの様子(大学6年)
コンピュータのソフトウェア作りに興味を持つ
私が色覚の研究をしていた頃は、まだわからないことが沢山ありました。特に色覚異常の保因者の特性がわかりませんでした。この女性が保因者かどうか、色覚正常な保因者と色覚正常な男子はどこが違うのか、などを調べる研究をしていました。その当時は大量のデータを扱っていたため、「初心者のためのフォートラン講習会」などのソフトウェアの講習会にも参加し、大型計算センターに入り浸っていました。最初はデータ処理をするために通っていたのですが、最後の頃はソフトウェアを作る方が面白くなってきまして(笑)。安間眼科の玄関に“待合表示器”がありますが、あのソフトも私が開発しました。安間眼科で使っている手術や検査の予約システムもエクセルのマクロと市販のラベルソフトとを連動させたものですし、職員の給与計算も自前のソフトです。不具合を見つけて一つずつ潰していくのは、けっこう楽しい作業です。本当は、医療より、そちらの方が向いているかもしれませんね(笑)。


趣味のテニスは学生時代から現在まで続いている。
カリフォルニア大学バークレイ校で基礎研究に取り組む
名古屋大学大学院を修了して名古屋大学附属病院に勤務していた頃、アメリカ国立衛生研究所の奨励研究員としてカリフォルニア大学バークレイ校に留学し、視覚の研究をしました。バークレイ校に行ったのは、色覚や視覚の仕事でいろいろアドバイスを頂いていた早稲田大学理工学部の大頭仁教授がバークレイ校の教授の仕事仲間で、紹介してもらったことがきっかけです。当時、最も感じたことは、臨床の合間に研究を片手間でやっても時間が足りないということ。その時の相棒はPhDといって、いろいろな研究分野のスペシャリストたちです。皆、すごく賢い人ばかりでした。PhDの人たちは専門でそれだけを一生懸命やっているのに、私が臨床をしながら研究をしてもかなうわけがありません。それで、研究をあきらめて臨床1本に絞り、帰国後には眼科臨床医としてやっていくことに決めました。

カリフォルニア大学バークレイ校での留学時代。

ホームステイ先の家の玄関で、近所の方たちと。

留学時代の研究室。光学機械がずらりと並ぶ。
大学勤務医時代から手術が好きでした

アメリカから帰国した後、名古屋大学でしばらく勤務をしていましたが、父が病気になったこともあり、1988年に父の跡を継ぎ、安間眼科3代目の院長になりました。眼の治療はその結果がすぐに自覚症状に反映する場合が多いです。殊に白内障手術がそうです。白内障が治って、喜んで帰っていかれる光景を見ると、私も嬉しくなります。大学勤務医時代から手術が好きで、白内障や角膜移植、網膜剥離や硝子体手術など、眼に関する手術はほとんどやっていました。当時、大学には外来係と病棟係があり、私は病棟係を長くやっていましたので、手術をする機会も数多くありました。
「紹介状」が内科医との大切なコミュニケーションツール
安間眼科の院長を継いだ時、「こうしていきたい」という明確なビジョンがあったわけではありません。ただ、「眼なら任せとけ」と胸を張って言える医師になりたいと強く思っていました。眼の病気は全身の病気の一部であるものも多く、内科の先生としっかり話し合える関係を作っていかないといけません。しかし、内科の先生と直接お会いする機会はあまり多くありません。たとえ近くにいても、内科の先生と眼科医を結ぶものは「紹介状」です。紹介状でコミュニケーションを取るのが一番の方法だと思い、安間眼科では紹介状を年間5,000通ほど書いており、そのうち半分くらいが入院関係です。眼科に診察を受けに来る人は、ほとんどが内科の主治医を持っていますので、患者さんの情報を紹介状に書いて、主治医の先生とコミュニケーションを取っています。紹介状をきちんと書くには、患者さんの身体の状態を聞かなければいけません。心臓が悪い人もいますし、血が止まりにくい薬を飲んでいる方もいます。そうした患者さんの状態を見落とさないようにしています。良い治療を提供するためには、内科の先生との信頼関係が必要です。紹介状の作成には毎日2時間近く費やしています。
最新の機器を積極的に導入
患者さんの身体をよく知って、正しい医療を提供するという当たり前のことが大切だと思っています。正しい医療を提供するためには、今ではさまざまな機器が欠かせません。眼にはいろいろな病気が出ます。例えば、結核も、梅毒も、ぶどう膜炎として目に出てきます。エイズもそう。もちろん、糖尿病や高血圧も眼に出ます。さまざまな病気で眼底に出血したり、血管が細くなって詰まったりすることがあります。結膜下出血を心配する人が多いけれど、あれは皮下出血のようなものなので大丈夫。ですが、眼の充血は炎症があることのサインなので違います。眼にはたくさん血管があるので、普通の人がぱっと見ただけでは、出血か充血かはわかりにくいですが、検査機器でみればすぐにわかかります。眼科というのは、検査をする科です。眼では見えないことを知るために、さまざまな検査機器が役立ちます。
父が手術をはじめた時代は、まだ手術顕微鏡がない時代でした。眼科で手術顕微鏡を普通に使うようになったのは、やっと50年程前からです。眼科ではさまざまな光学機械を使うので、光学機械が進歩すると眼科は進歩します。手術顕微鏡も昔は性能が良くありませんでしたが、性能が良くなって眼科の手術はものすごく進歩しました。昭和40年代に手術顕微鏡が普及し、眼内レンズが昭和50年代、硝子体の手術が一般化したのもその頃からです。そして、ここ最近の10年間でさらに機械が進歩しました。この背景にはコンピュータの進歩と小型化があります。ハイテクのコンピュータで制御して、ほんのわずかな時間差を見ることも可能になりました。目の中は透明ですから、目は血管を体外から直接見ることができる唯一の臓器です。網膜の血管の状態を見るには、血管の中に色素を入れて撮影する血管撮影が以前は主流でしたが、今はコンピュータの進歩で、血管の中の血球の動きをディテクト(探知)できるようになりました。すると時間差で見て、動いたものがある場所は血管だという判定ができます。これによって、造影剤を注射しなくても血管撮影ができるようになりました。ものすごく進歩していますね。例えば加齢黄斑変性症のような場合、造影剤を注射しないと新生血管がわかりませんでしたが、OCTAというコンピュータを使って時間差で見ていくプログラムを使うことで、造影剤を注射しなくても診断ができるようになりました。網膜を各層に分けて、どの層に血管があるかもわかります。とても画期的な検査機器です。こうした新しい機器がでてくる眼科分野というのは、非常に面白いですね。
「眼科ジャーナル」で最新の論文を紹介
安間眼科のホームページに「眼科ジャーナル」を作り、眼科に関する最新の論文を掲載し、過去の論文もアーカイブとして保存しています。これはもともと大学病院に勤務していた時の仲間たちと「勉強会をやろう」という話が出て、最初は症例の検討会を考えたのですが、興味を引く症例が毎回出せる訳ではありませんので、勉強会の目玉として論文の紹介を始めたことがきっかけです。診療所を建て替えた1995年に15、6人で始め、今も20人位が集まってやっています。外国の雑誌や日本の雑誌、合わせて20冊くらいを抜粋して紹介しています。最初は私の独断で紹介する論文を選んでいたのですが、途中から安間眼科に勤務する医師も加わってくれるようになりました。興味深いことに、選ぶ論文が皆違う。面白いと思うものは人によって違うことを実感しました。
勉強会は2ヶ月に1度のペースで行っていますので、もう130回を超えましたが、ホームページの「眼科ジャーナル」もそのタイミングでまとめて更新しています。医学の最近の進歩というのはジャーナル(雑誌・専門誌)でしか分かりません。もちろん学会や講習会に行けば良いのですが、欧米のジャーナルに載っている眼科の進歩はすごいです。今、世界では何をやっているのだ……というのを見るのは面白いですね。まぁ、半分は趣味ですが(笑)。

安間眼科ホームページに開設している「眼科JOURNAL」
色覚への理解を深めるために
〜愛知県眼科医会会長に就任して〜

愛知県眼科医会会長として最後に取り組んだことは、色覚検査に対する理解です。色覚検査は検査機械によって違う答えが出る場合があります。正しい診断はアノマロスコープという器械でしかできませんが、アノマロスコープはそれほど多く普及していないので、すべての眼科医療機関で使える訳ではありません。一方、色覚異常は先天性のもので変化するものではありませんので、その診断はどこの眼科医療機関に行っても同じでなければ眼科医の信用がなくなります。すべての眼科医療機関で同じ診断がつくようにするためにはどうすればいいかを考えていました。まずは、多くの人に色覚検査を受けてもらって、自分の色覚特性を知ってほしいと思います。
現在、色覚検査は義務化されておらず、希望者だけが受けることになっています。何歳に検査するという決まりもありません。どこで誰が行うかについてもまだ決まっておらず、これから決めていく必要があります。例えば、学校で検査する場合、学校医が行うのか養護教諭が行うのか、一般の眼科医療機関で色覚検査を行った場合には当然、医療保険が適用されるのですが、学校医の医療機関で検査を行った場合、医療保険が適用されるのかどうかも決まっておりません。その辺も難しいところです。
名古屋市が全国でいち早く学校での色覚検査を中止した経緯に私が関わっており、愛知県眼科医会の会長をやっていた時に色覚検査が再開されましたので、色覚の課題への取り組みは運命みたいなものかもしれませんね。
最新の医療をできる限り早く臨床に取り込む
〜眼科医療のこれから〜
眼科医療のこれからを考えた時、認められた最新の医療をできる限り早く臨床に取り込むことが、開業医のレベルでは大切だと思います。例えば働き盛りの人がなりやすい加齢黄斑変性症です。働き盛りの人には良い視力が不可避です。視力が落ちると、本当に不便です。そういう病気に対してもできる限り早く対応していくことが、私たち開業医の役割です。
ただ、患者さんの主観には個人差が大きく、例えば「1.0が見にくいから白内障手術を受けたい」と言う人もいますし、視力が0.3とか0.4まで落ちた人でも「まだ十分見えるからこのままで良い」と言う人もいます。その辺の見極めが大事で、患者さんの性格まで知らないと最適な治療は難しいと考えています。そのためにも、私たち医師よりも患者さんと対応する時間が長い看護師やORT(視能訓練士)などのスタッフが患者さんと事前にゆっくり話をして、その人の性格やその人が何を求めているかまでキャッチすることが大切だと思っています。
医療にとって一番大事なことは、まずは受診してもらうこと。患者さんに信頼され、安心して治療を任せていただける安間眼科であり続けたいと考えています。
インタビューを終えて
3代目院長として安間眼科を継いで30年。地域の眼のかかりつけ医として信頼を集める一方で、日々、最新の機器や治療に関心を持ち、海外の論文にもしっかりと目を通されています。その研究熱心な姿勢は学生時代から変わることなく、だからこそ安間先生の技術は高く評価されています。
患者さんを優しく見守る目、そして地域の未来を見つめる目。両方を兼ね備えているからこそ、愛知県眼科医会の会長という責務も任されたんだと思います。